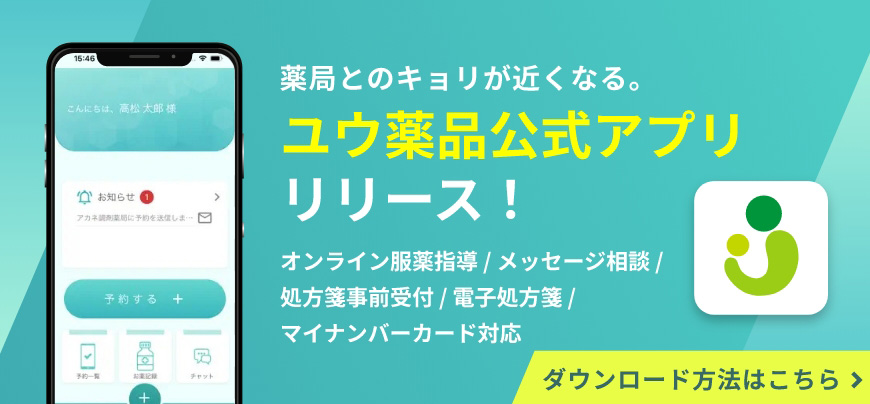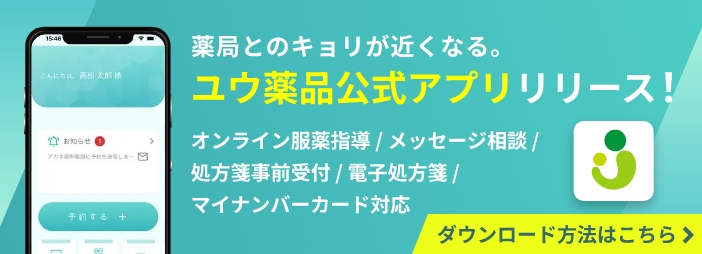お知らせ・ブログ
防災士-薬剤師Oによる 防災基本講座 その7
自助 共助 公助について・・・
9月1日は、「防災の日」です。 関東大震災(1923年)の発生日です。
地震だけでなく、水害・火災など色々ありますが、大きな災害が、自分の身に降りかかってきた場合どう対応しますか?
一般に災害被害の軽減は、「自助・共助・公助」の効率的な組み合わせで実現されます。
過去6回では、主に自分でできる防災対策⇒自助について書きましたが、今回は共助と公助について書かせてもらいます。
先に、公助についてですが、住民の生命・財産を守るために国や自治体・消防・警察・自衛隊などによる救助活動・避難所の開設・救援物資の配布・仮設住宅の設置などが行われます。
また事前の対策としてインフラの整備・耐震化工事・避難路の確保・避難場所の整備・建築物の耐震化への助成・公共施設の耐震化・災害関連情報の周知・事前対策の整備などハード対策・ソフト対策を行います。共助について、
先に述べた公助は、公共施設の耐震化などはいいのですが、いざ大規模災害が発生した場合。
すべての人に十分な救助・避難所・救援物資を送り届けるのは残念ながら無理です。
また、個人の力で巨大な被害を防ぎきるのも限界があります。
そこで、災害時、地域で協力して被害を最小限に抑えたり、被災した人を救助することが必要です。
これが共助です。災害発生直後の救助は周りにいる人にしかできない。
そのため家族・近所の親類・近所 町内会ぐらいの規模での助け合いが必要になります。日頃から町内会や自主防災組織などの人達と顔見知りになるようにし、近所付き合い・防災訓練で、いざという時に協力して対応できるように仲間作りを、しておくことが重要です。
災害時の公的救援が十分でない時の近隣地域住民同士の助け合いは、救出・救援・災害時用配慮者のサポートやケアなどにおいても大きな力になります。地域住民だけでなくボランティア(個人・団体)・企業などからの支援・活動も大きな役割を、になっています。
社会のあらゆる人的・物的資源を動員して防災・減災対策を行っていきましょう。写真は、町内の自主防災会による避難訓練の様子です。
津波到達時間までに、高台へ徒歩で避難する訓練です。
液状化などの障害物の発生を想定しながらの集団で安全にまとまって移動することの難しさを体験しました。